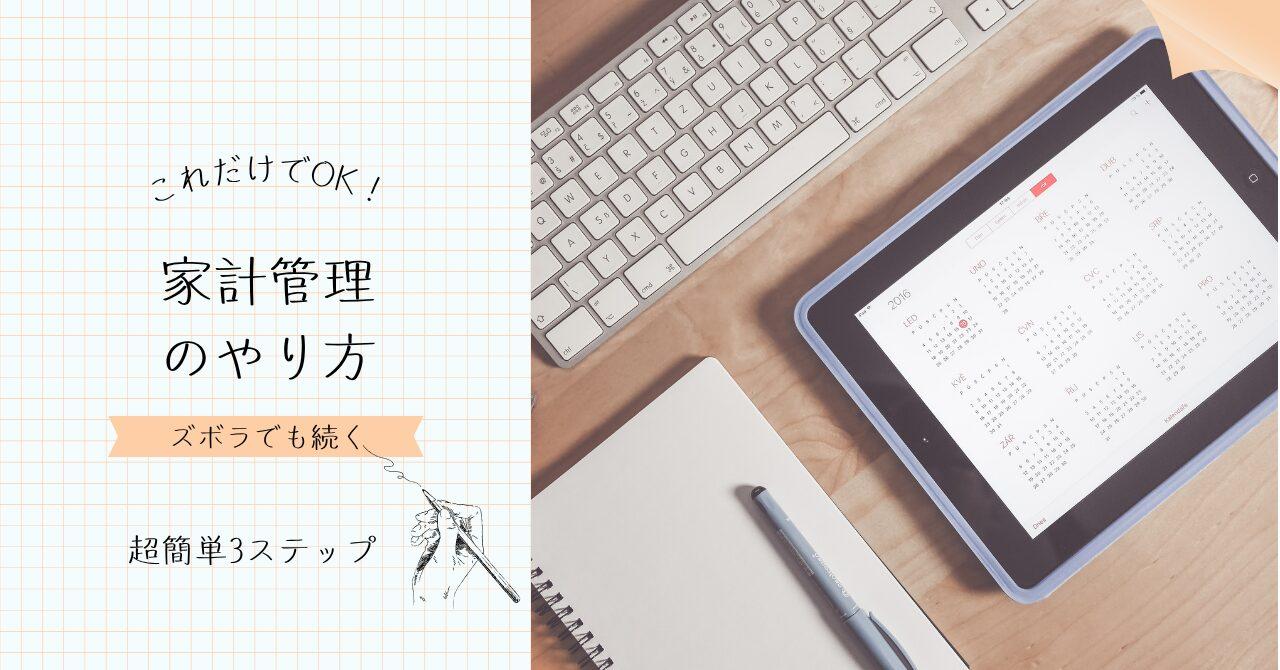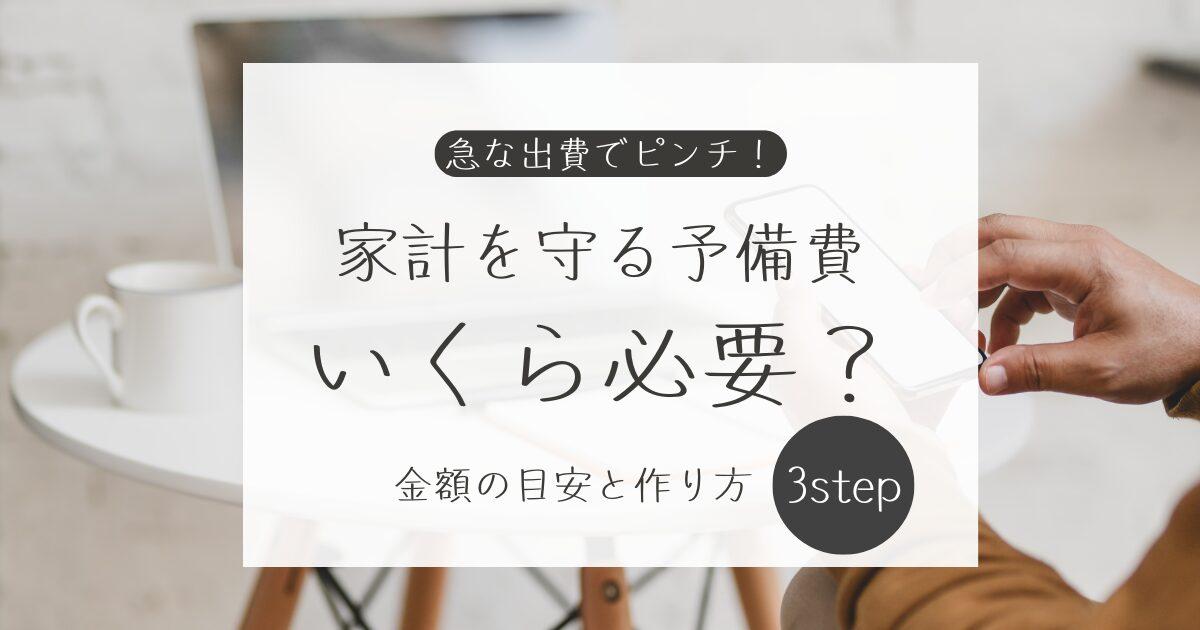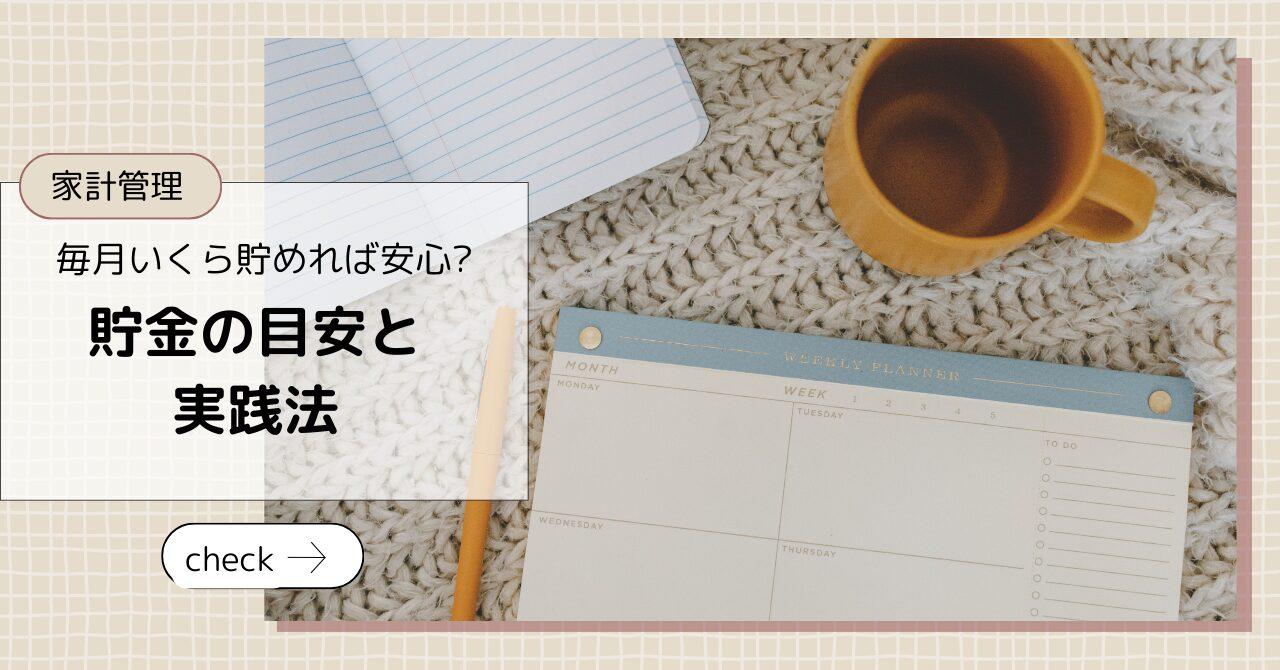- 家計簿をつけても続かず、いつも三日坊主になってしまう
- 家計管理のやり方が難しそうで、何から始めたらいいのかわからない
- 共働きだけどお金が貯まらず、将来が漠然と不安
家計管理が大切なのは分かっているけど、
「そもそもやり方が分からない」
「面倒で続かない」
「つけてるだけで貯まらない」
…そんなふうに感じていませんか?
実は、家計管理がうまくいかないのはやり方が難しいからではなく、“最初の設計”に無理があるからなんです。
この記事では、ズボラでも無理なく続けられる家計管理のやり方を初心者向けに解説します。
手書き・アプリ・袋分けなど、あなたに合った方法を見つけるヒントから、予算設定やお金の見える化のコツまで、ステップ形式でご紹介します。
この記事を読み終えた頃には、「これならできそう」「ちょっと試してみたい」と思える家計管理の一歩がきっと見つかります。
家計管理とは?初心者向けの基本概念
家計管理とは、収入と支出のバランスを把握・調整し、将来に備えてお金をコントロールすることです。
家計管理を実践することで得られる最大のメリットは、「お金の不安が減ること」。
実際に自分が何にどれだけ使っているかを可視化することで、ムダな支出に気づけるようになります。
たとえば「毎月何にいくら使っているのか」が分かるだけでも、意識が変わります
つまり、家計管理は「節約のため」でもありますが、「自分の人生を自由に設計するため」の手段でもあります。
生活費の目安は収入の6割~7割
おおまかにでも生活費の目安を知っていると、無理のない予算を立てやすくなります。
例えば、総収入の6割から7割を生活費に充てるのが一般的な目安とされています。
この基準をもとに、自分の支出を見直し、家賃や食費、光熱費などの各項目に適切な予算を割り振っていきましょう。
最初は無理のない金額を設定し、予算が余ればその分は翌月分の予算からカットするなどで対処していきます。
住居費(家賃や住宅ローン等)は、住んでいる地域や物件による金額の差が大きい項目です。固定費のなかで特に高額になるので、場合によっては引っ越しも視野に入れ、見直してみてください。
家賃は、手取り月収の3割程度に抑えるのが一般的な目安です
共働き夫婦における家計管理の役割分担
共働き夫婦にとって家計管理は、家計の「見える化」と「役割分担」が鍵になります。
収入の柱が2本ある分、ついお金を使ってしまうという罠を避けるためにも、「お互いの収入を知らない」「これぐらいなら使っても大丈夫だろう」といった不安要素はできるだけ排除したいですね。
夫婦で「食費や水道光熱費などは夫、固定費は妻」といった役割分担をするだけでも、管理はぐっとラクになります。
- 給料が入ったら、お互いに一定額(収入の5割など)を天引きで共有口座に貯蓄する
- 夫の給料だけで生活し、妻の収入は全部貯蓄・投資に回す
- 夫婦二人の手取り月収の、2割を貯蓄に回す
自分のお給料を家計に全振りだと、やはりストレスが溜まったり、気持ちがくさくさしますよね。
ご褒美システムやおこづかい制を導入するなど、お互いに無理のないやり方を見つけてください
家計簿の書き方とそのコツ
家計簿をつけ始めるとき、多くの人が「どうやって記録すればいいの?」と悩みます。
アプリ、市販の家計簿等、記録方法はいろいろありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。
まずは基本を押さえて、自分に合う方法を見つけることが大切です。
初心者向け:家計簿の基本的なつけ方
家計簿を始めるなら、まずは「毎日つける」ことよりも、「大まかに全体像を把握する」ことを重視しましょう。
家計簿は細かく記録するより、「何にどれくらい使っているか」がわかるようになればいいのです。
「週に1回レシートをまとめてチェックするだけ」「家計簿アプリでレシート撮影するだけ」など、ハードルの低い方法からでOKです。
項目を細かくしすぎると、「この支出はどの項目なの?」と混乱してしまいます。
家計簿に必要な項目と固定費・変動費の把握
固定費(毎月決まって出ていくお金)と変動費(その月ごとに変わる出費)を分けて管理すると、家計の見直しがしやすくなります。
固定費
家賃(住宅ローン)・通信費・保険料・各種ローン・駐車場代・サブスクリプション代など
変動費
食費・外食費・日用品・交際費・娯楽費・被服費・医療費など
この項目を全部使う必要はありません。
あなたの生活に合うようシンプルに分けることで、どこに無駄があるかが見えやすくなり、改善にもつながります。
固定費と変動費は、どちらもバランスよく見直しが必要ですよ
ズボラでも家計簿が続くコツ3つ
基本の書き方が分かったら、さっそく実践です。
やる気のある最初だけ!ではなく、ズボラさんでもゆる~く続けられるコツを3つ紹介します。
コツ1:家計簿の項目はざっくり決める
家計簿をつける際、支出項目を細かく分類しすぎると、毎回の記録が面倒になり、挫折の原因になります。
たとえば「食費」「日用品」「娯楽費」程度のざっくりとした分類にすることで、記録がグッとラクになります。
もっとざっくり、「消費」「投資」「浪費」に分類するだけでもOKです。
最低限の分け方で管理することで、気軽に続けられますし、支出の傾向も十分に把握できます。
コツ2:1円単位まで合わせようとしない
毎月の収支を1円単位までピッタリ合わせようとすると、時間も手間もかかり、やる気が削がれてしまいます。
100円以内の誤差は「誤差として扱う」くらいの柔軟さを持つと、継続がラクになります。
厳密さよりも「全体の流れをつかむこと」が大切です。
完璧を目指さずに大まかな管理を意識することで、ストレスなく続けられます。
コツ3:手書き vs アプリ?自分に合った方法を使う
家計管理は人それぞれ。手書きの家計簿が合う人もいれば、アプリやExcelの方が向いている人もいます。
大切なのは、「周りが使っているから」ではなく「自分にとってラクな方法かどうか」で判断することです。
たとえば手書きは自由度が高く、項目も自由に決めやすいのがメリットです。思考の整理にも向いています。
スマホでサクッと入力できるアプリなら、スキマ時間に記録しやすく、計算も自動でしてくれるので、負担も少ないですよね。
自分に合う方法を見つけることで、自然と習慣化しやすくなります。
袋分けの活用とそのメリット
袋分けは、予算をあらかじ項目ごとに分けて現金で管理する方法で、使いすぎ防止に効果的です。
毎月使えるお金を「食費」「交際費」「日用品」などに分けて予算分を封筒に入れておくと、使える金額が明確になります。
食費などはもう少し細かく週ごとの予算を決め、1か月分5週間で管理するのがおすすめ。(1週間分はお米や調味料等に充てる)
袋分けにするとその週に使っていいお金がいくら残っているのかが分かりやすいので、家計管理初心者や現金派の人には特におすすめです。
こういった便利アイテムはぜひ取り入れてみてください。
実践!家計管理の具体的な3ステップ
理論を詰め込むだけでなく、実際に手を動かしてみましょう。
具体的なステップを踏むことで、家計の状況が明確になり、改善点も見えてきます。
ここからは、実践に役立つ3つのステップを順に解説していきます。
STEP1:毎月の支出を把握する
まずは毎月の支出を把握することが家計管理のスタートです。
レシートを保存したり、家計簿アプリに記録したりすることで、どこにいくら使っているかを明確にできます。
支出を把握することで、むだ遣いに気づき、節約すべきポイントを見つけやすくなるため、効率的な家計管理が可能になります。
「家計簿は初めて」というあなたは、まずは1週間分から始めてみてください
STEP2:お金の流れを整理する
次に、お金の流れを視覚的に整理しましょう。
ここは以下のようなツールを活用することをおすすめします。
- 家計簿アプリ
- Excel
- Googleスプレッドシート
- 市販の家計簿
- ノート
これにより、何にどれだけ使っているのか把握しやすくなり、改善点を具体的に見つけやすくなります。
毎月、さまざまな引き落としが発生すると思いますが、引き落とし専用口座を作ると管理がしやすくなります。
給料が入ってくる口座と同じでもいいですし、別の口座を専用にしもいいです。あちこちに分散しているより、管理がしやすくなります。
STEP3:家計の見直しをする
収支の記録を継続する以外にも、定期的に見直すことも大切です。タイミングとしては、1か月に1度の頻度でもOK。
見直しをすることで、無駄な支出や予算オーバーしている項目に気づけるからです。そうすると、その時点で改善策を立てられます。
毎月末に1か月分の家計簿を振り返り、次月の予算を調整する習慣をつけると、より効果的な家計管理が実現します。
書いたから終わりにならないよう毎月の締め日に点検しましょう。
家計簿を毎月1日~末日でつけると、転職して給料日が変わっても継続しやすいですよ
家計管理におけるクレジットカードの活用法
クレジットカードは正しく使えば家計管理の強い味方になります。
支出の履歴が明確になり、ポイント還元などのメリットも享受できるからです。
ただし、使いすぎには注意が必要です。
カードで支払った金額は、引き落とし用の封筒を別に用意して取り分けておくと、来月に請求額を見て焦る心配が減ります。
家計管理を長続きさせる方法4選
家計管理は続けることがむずかしいですよね。
大切なのは「無理なく続けられる」工夫を取り入れること。
以下では、長続きのための具体的な方法をご紹介します。
週単位で管理する
毎日家計簿をつける時間なんて取れない!という忙しいあなたは、週単位での管理がおすすめです。
もらったレシートは封筒や空き箱に入れて保管しておき、記録自体は週に1日だけ時間を作るといった方法があります。
事細かに項目が分けられた複雑な家計簿より、シンプルに記録できる家計簿を選ぶのが肝心です。
週末の夜に家計簿をつけると、翌週の予算の見直しも同時にできますよ。
貯蓄目標額は具体的に決める
まずは「いつまでに」「いくら貯めたいか」を具体的に決め、そのために毎月いくら貯蓄すべきか計算しましょう。
ただやみくもに「毎月〇万円貯める」より、「来年の夏に旅行に行くために50万円貯める」といったように、貯蓄は具体的な目的と金額を決めるのがおすすめです。
貯蓄目標の立て方についてもっと詳しく知りたい!という方はこちらの記事をご覧ください。
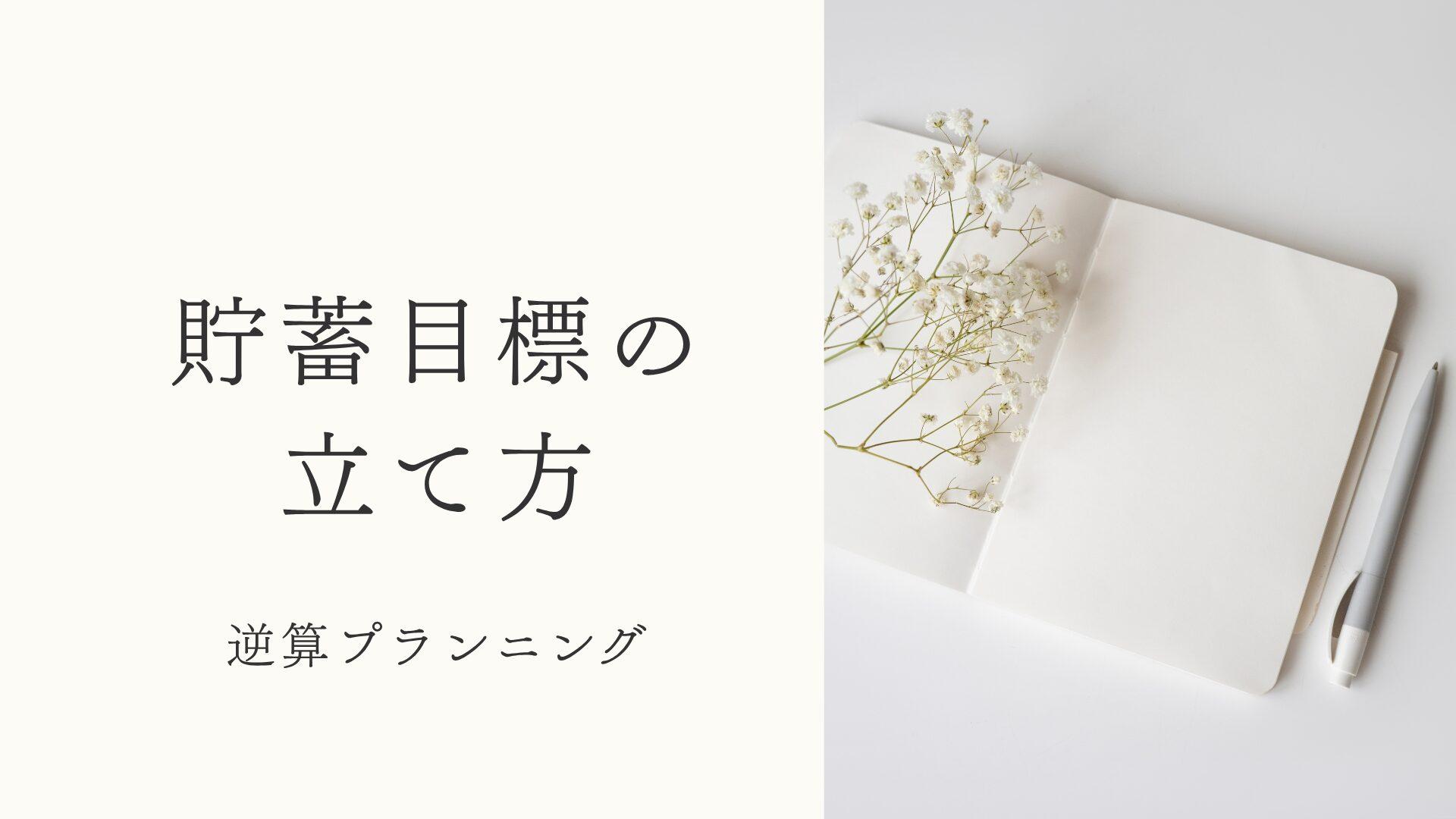
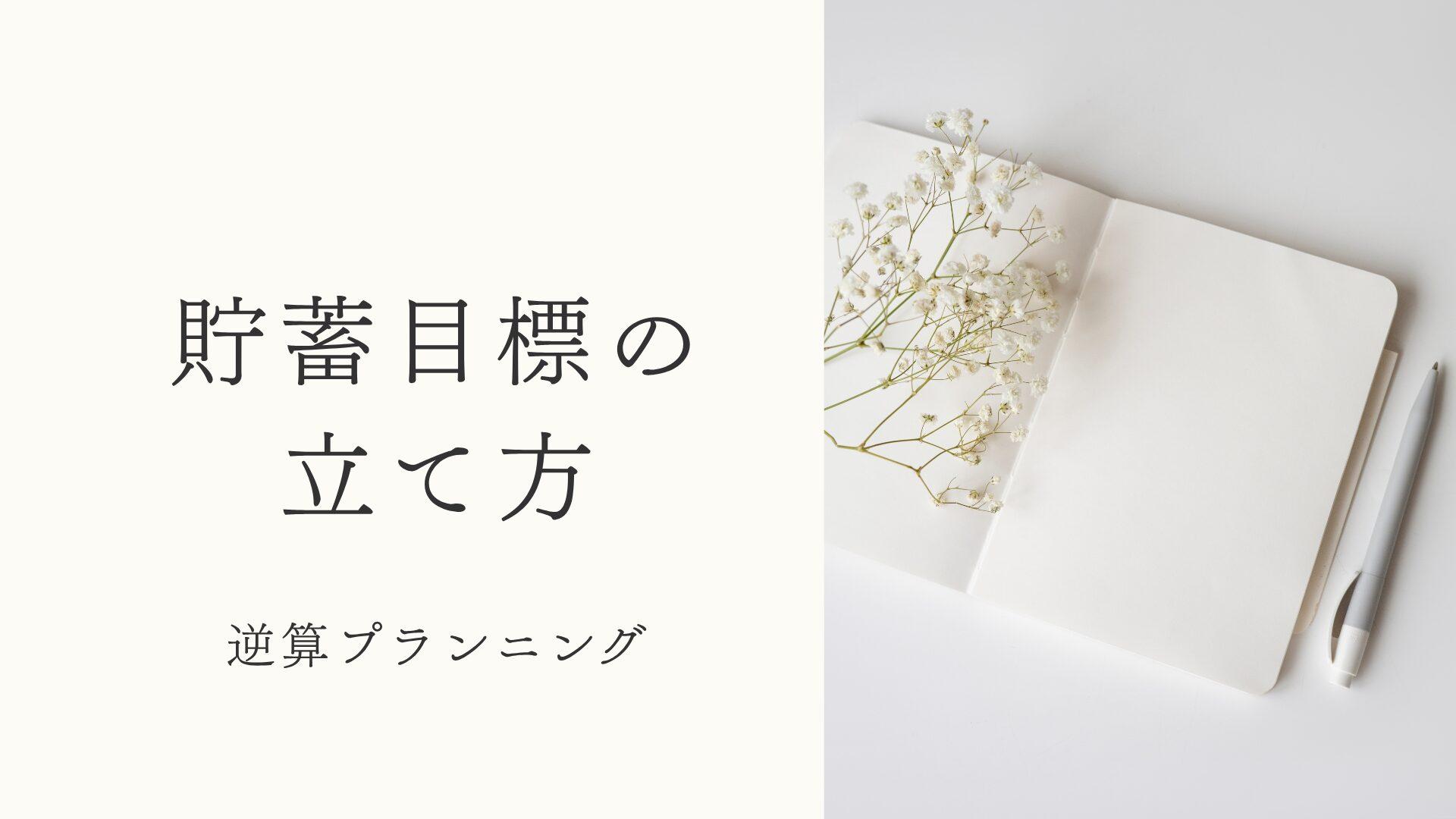
家族やパートナーと共有する
家計管理は、家族やパートナーとの協力が不可欠です。
あなたが節約を頑張っているのに、その隣でむだ遣いを繰り返されると、ストレスになりますよね。
「何のために貯蓄するのか」、「家計がこんな状態だからこの項目は2割は減らしたい」といった話し合いの時間を持ってみませんか。
家計簿を見せながら家族会議をすれば、価値観のすり合わせにもなります
一人暮らしの人も、家計の見直しを定期的に行い、友人やSNSのコミュニティに参加して情報交換をするのも継続の助けになります。
見直して分析する
定期的に見直して成果を振り返ることが、家計管理の継続には有効です。
家計簿を記録するだけで終わらせず、毎月の貯蓄額や支出の減少をチェックし、具体的な数字で改善を実感しましょう。
結果が目に見えるとモチベーションが上がりますし、さらに改善ポイントを探したり、ほかにできる工夫はないか、意識が前向きになります。
まとめ:ズボラでも続く家計管理のポイント
家計管理は難しいイメージがありますが、コツを押さえればズボラでも続けられます。
無理なくできる方法を見つけ、目標を明確に持つことが継続の第一歩です。
最後に、本記事で紹介したポイントをまとめておきます。
- 家計管理はお金の流れを把握し、むだ遣いを減らす基本から始めること
- 手書きやアプリ、自動化など、自分に合った家計簿のつけ方を選ぶこと
- 生活費の目安や貯蓄目標を立てて、具体的に管理すること
- 毎月の支出把握やツール活用で、家計の改善を継続すること
- パートナーとの協力やモチベーション維持の工夫を取り入れること
物価高騰でこれ以上削れるところはない…というあなたは、副業を始めることを考えてみませんか。
もちろん勤務先が副業(兼業)可能という前提はありますが、これ以上削れないなら「収入を増やす」方向に目を向けるのも、新たな一歩です。
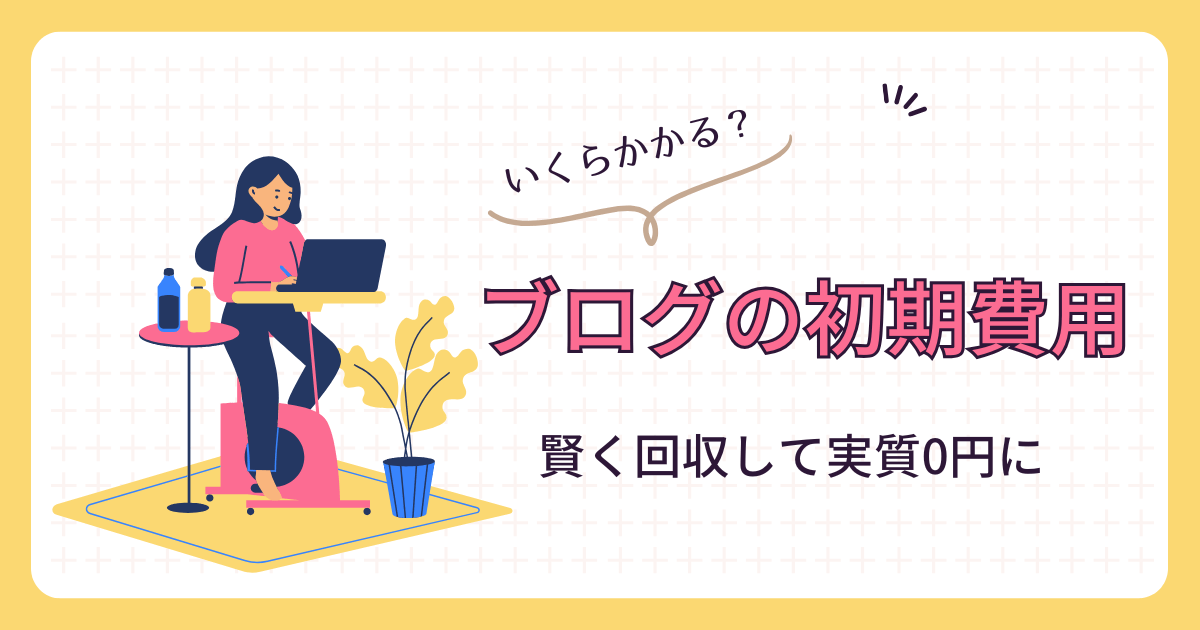
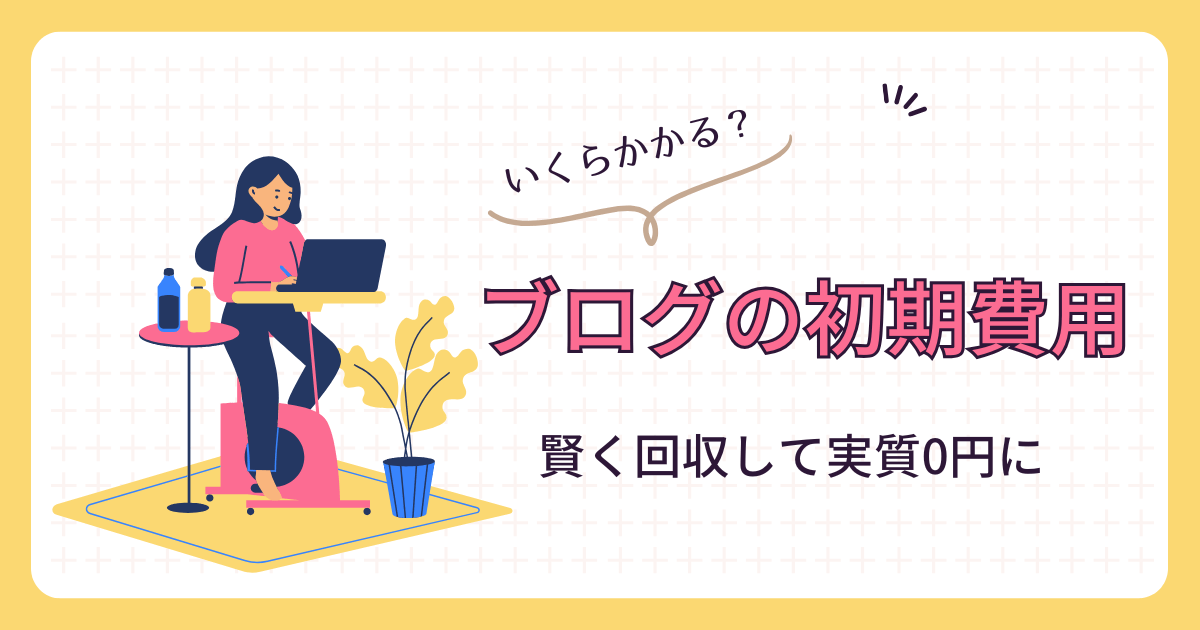
ではまた!